おはようございます、 本日の投稿は株式会社GUILD CARE(ギルドケア)が担当します。
先日、滋賀県で開催された「第12回生活困窮者自立支援全国研究交流会」に参加してきました。
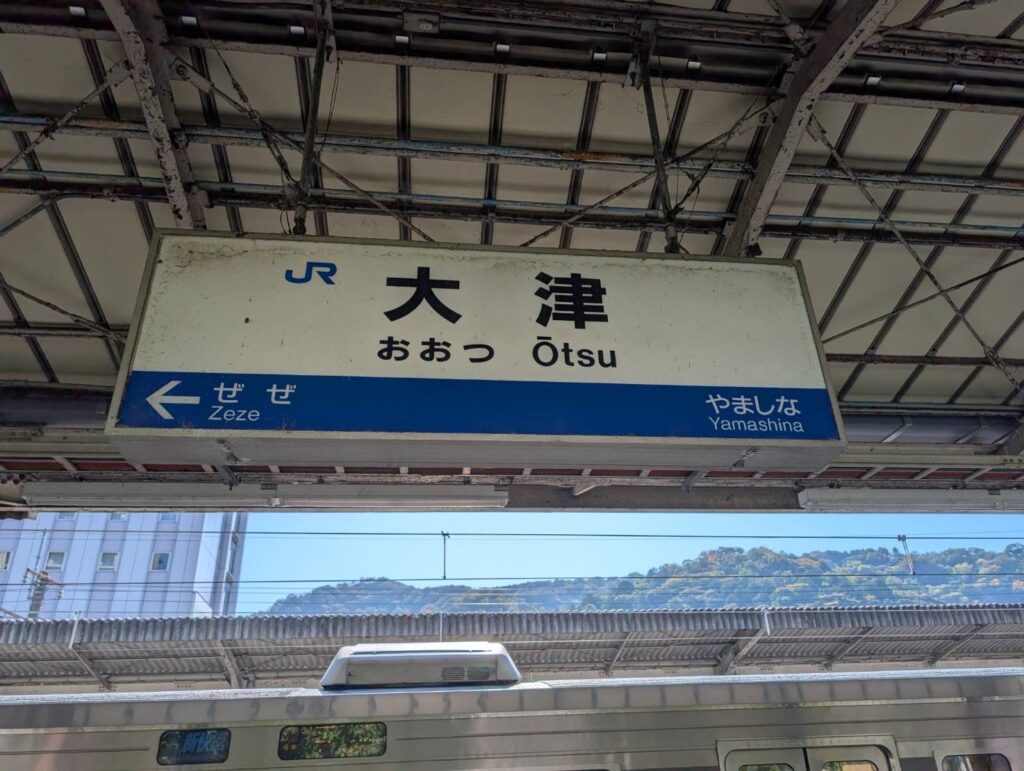

朝から移動し、初めて足を踏み入れた会場の空気は独特で、緊張と期待が入り混じる感覚が胸の奥に広がります。
今回のテーマは「視界が開けない時代だからこそ、生活困窮者支援で作り出したい地域共生社会」。
この言葉の重みを、会が進むほど深く噛みしめることになりました。

全国から支援者が集まり、それぞれが抱えている現場の悩みや成果を持ち寄って語り合う場は、まるで大きな知恵袋のようでした。
制度の限界に直面した時の疲れや迷いを共有する一方で、新しい支援の形が芽生えた瞬間の明るい話題も聞こえてきます。
良いことだけでなく、支援しているからこそ感じるつらさや葛藤までテーブルに並べられる雰囲気があり、「現場では皆さんも同じように戦っているんだ」と妙な安心感を覚えました。
こうして集まり、経験をつなぎあう時間があることで、支援者もまた支えられているのだと気づかされました。

研修後に開催された大懇親会では、さらに踏み込んだ交流が生まれました。
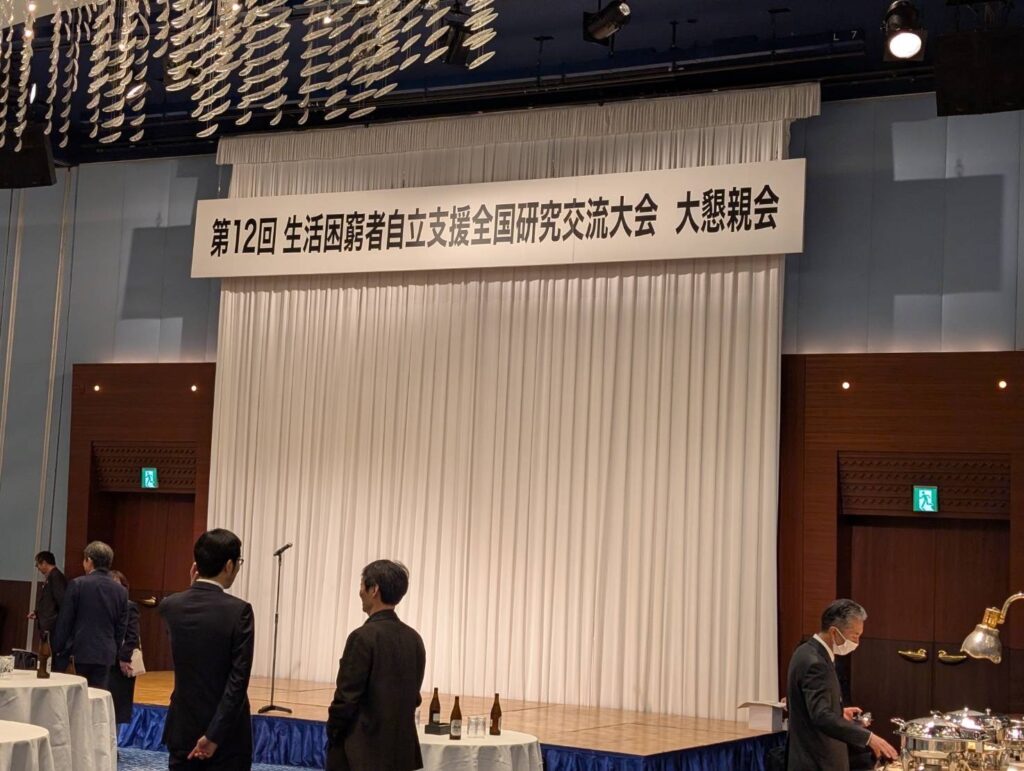
食事を囲みながら聞く話は、会議室とはまた違う温度を持ち、支援に込める思いや葛藤がよりリアルに伝わってきます。
肩書きも立場も関係なく、同じ思いを胸に抱く者同士が語り合うこの空間は、どこかほっとする温もりを感じさせました。
緊張していた表情がふっと和らぐ瞬間があちこちで見られ、心の距離が一気に縮まっていくのを感じます。

今回の研修は、新しい知識や手法を得ただけでなく、「支援者がつながり続けること自体が、地域共生社会の第一歩なのかもしれない」と気づかせてくれました。
人と人が手を取り合えば、小さな光は確かに生まれます。
その光を絶やさないよう、私たち自身もまた明日からの支援に向き合っていきたいと思いました。










